ツアーレポート:それぞれのアンラーニングの旅は続く
- ナマケモノ事務局

- 2025年11月13日
- 読了時間: 12分
9月1日~9日まで、ナマケモノ倶楽部とジュレー・ラダック共催で、「"懐かしい未来"の故郷で、豊かな自然と文化の未来をみつける旅」を開催しました(ツアー詳細はこちら)。
数回に分けて、旅の日記と、貴重なインタビューなどをこの「ナマケモノしんぶん」でシェアしていきます。私たちが実際に目でみて、村に身を置き、人々の話から感じた学び・気づきをみなさんが受け取り、これからのローカリゼーション運動の知のツールとして活用いただければ幸いです。(事務局)
9日目(最終日)

レー市内のホテルで朝食、そしてレー空港へ
いよいよ今日が最後です。昨晩も雨が少し降り、宿泊したZikzik Holidaysのきれいな庭の緑がきれいでした。8時からのラダック最後の朝食。9時半の出発まで、テラスでゆっくりお茶を飲みながら語らったり写真を撮ったりと、それぞれの人が名残惜しそうに時間を過ごしていました。
空港では、何日も一緒に過ごしたタクシードライバーさんやスカルマさんとの別れ。言葉の通じきれないところもありましたが、ただただ感謝の気持ちでいっぱいでした。
空港に入れば事務的な手続きが始まり気持ちもあわただしく、それぞれ搭乗する飛行機も異なり、特に遅れている便をボーっと待つことになりました。結局、私の便が一番最後となりました。少し雨がぱらつく中での出発でした。最初見た飛行機からの景色は、人の気配なんて感じられませんでしたが、今は、あの少ない緑の中に豊かに暮らしているラダックの人々の姿が思い浮かびました。
今回のラダックの旅でもたくさんの宝物をもらった気がしました。その宝物を自分のものだけにせず、私のこれからの人生、そして周りの人たちに手渡せていけたらと思います。(ともえ)

旅を通じてのメンバーたちの感想
●伝統的な暮らしを続けているラダックの村の人々に混じり生活することができ、その平和さや逞しさに感動しました。住居・食料など自給している姿、また仏教の影響なのか人々が全体的に穏やかで優しい事が印象に残っています。
ラダックを訪れる前から自然が美しい場所という印象を持っていましたが、ツアーを経て、文化の面でも貴重なものを持っている土地なんだと感じました。グローバリゼーションの波に負けず、技術発展の恩恵を受けつつもラダックのローカルな良さを維持して「懐かしい未来」へ進んでいって欲しいです。(りょうすけ)
●ラダックで過ごした日々をふりかえると、そこにあったのは“私たちの時間”でした。自然のリズム、人々の暮らし、仲間とのつながり。すべてがゆるやかに重なり合い、静かに流れていました。
旅に出る前の私は、世界の速さや情報の多さに飲み込まれ、自分のペースを見失っていたように思います。けれど、ラダックでの暮らしにふれながら、自然と共に呼吸する時間の中で、「生きる」ということの根っこを改めて感じました。知れば知るほど、世界は複雑で、美しさの奥には痛みや矛盾もありました。それでも、それを避けるのではなく、抱えながら共に生きる人々の姿に、本当の強さと優しさを感じました。
この旅を通して大切に育んでいきたいことは、希望は日々の小さな実践の中で、少しずつ育っていくということ。これからも、あの土地で感じた「わたしたちの時間」を思い出しながら、子どもたちや身近な人たちと共に、遊びや暮らし、語り合いの中から“私たちの未来”を再創造していきたい。そして、言葉以上に受け取った世界への“わくわく”を、体現できる人でありたい。この旅で出会った人々の物語を、どんな形になるかは分からないけれど、つないでいきたいな。(ももか)
●初めてのインド、そしてその場所がラダックだったことは、私の心に深く刻まれました。通訳という形で少しでもお手伝いできたことに、とても感謝しています。パラダイス・シェで出会ったスカルマ、ラモ、アモ、オッチ、それぞれの方が私に与えてくれた優しさや温もりは、言葉では言い表せません。
フェスティバルで出会ったシャーマン、毎日の美味しいごはん、そしてラダックの人々の優しさ──どれも強く心に残っています。また、日本からの友人たちとの会話もとても楽しく、私の拙い通訳にも温かく接してくれたことに感謝しています。(みき)
●敬愛する詩人ナナオサカキの「ラブレター」は、「半径1メートルの円があれば 人は 座り 祈り 歌うよ」で始まります。旅を終えて、何故かこの詩が脳裏をグルグル巡っています。シャラ―村で辻先生がお母さんたちに「今までで一番幸せだったことは?」との質問に「正月の5日目に村のみんなで集まって歌い踊ること」との回答がありました。
今回のラダックでの村の訪問やインタビューなどで感じたのは、ラダックの方々が、自分、他者、自然とつながり、余剰物を共有する、「金銭」を介しない相互依存のコミュニティ(=パスプン)で幸せに暮らしている姿でした(まさにパーマカルチャーの倫理そのもの)。その精神性は、チベット仏教により育まれてきたというスタンジン監督のお話は、スカルマさんから五体投地のやり方とともに教えていただいたマントラ(「…私の行ったすべての行為(業)がすべての生きとし生けるもののためになりますように」にも通じます。どこに行っても「カタ」(相手に敬意と祝福を込めて贈る白いショール)で歓迎してくださり、真心をもって接して下さり、我々が楽しんでいることを我がことのように楽しんでくれている人たちでした。(まさ)
●7日目の出来事ですが、スカルマさんが、私の「ラダックの籠が欲しい」という要望に応えてくれたのでお礼を言うと、「お客様は神様ですから」とキランキランの目で応えてくれた。邪な考えは全くなく、心からお客様を想っているその姿は、キランキランでした。スカルマさんのように、ラダックの方々のように、落ち着きを持ってありのままでいられたら、そして表現できたらと思う今日この頃です。
伝統的な食事を丁寧に作る、私たちのために用意してくれた暖かい寝具、手編みの靴下やお土産にドライフルーツの入った炒った大麦etc…。一つひとつのやり取りに思惑が全くなく、ひたすら聞く聴く、答える応える、そしてお互いに微笑む。スーッと入ってくるかどうかも分からない程の軽さが心地よく、私もそうなりたいと、その秘訣を探る日々。今回の旅は、 "ありのまま"と"おもてなし" という日頃探究していることを見させて頂いた旅でした。(のりえ)
●ラダックの旅を終え、とても人が住んでいるとは思えなかったのが、川に沿った緑豊かな土地の周りに作物を作り、家畜を育てて、自給自足にほぼ近い暮らしをしている人たちがいることがわかりました。私たちよりずっと心が満たされて生きていると思いました。ラダックでの村人たちとのかかわりは心地良いものがありました。この心地よさを自分の周りの人たちと共に取り戻したいと思いました。
還暦を過ぎたころから、私は次の世代に何が残せるのか、何が手渡せるのかずっと考えるようになりました。そしていろいろ試行錯誤する中、これまでしてきた食を一番手渡したいと思うのは小さな子どもを持つお母さんたちであり、それはマニッシュ・ジェインさんが言っていた考え方と同じでした。またサティシュ・クマールさんは、自分たちの手の可能性をいつも語ります。
サティシュの言葉に触発されて、今、自分たちの手で廃材をもらってきてみんなが集まる場、「まなの家」を作っています。屋根は捨てられていた杉皮です。「まなの家」を、ラダックで感じてきたような、心地よいコミュニティの場にしていきたいです。スローガンは「食からの平和、土からの平和、そして子どもたちからの平和」です。
今まで多くの方の素晴らしい話を聞き、本を読み、そんな場にも行ったりしてきました。そして、「すごいですね、素晴らしいですね」とたくさん言ってきました。でも言っているだけでは何も変わらなくて、ちゃんと具現化した場を作りたいのです。言葉や書いたりするだけでなく、来た人が体感できる場を作っていきたいのです。そういう意味でも、ラダックではたくさんそのヒントをもらいました。(ともえ)
●「オン マニ パドマ ホン =生きとし生けるものが 苦しみから逃れ 幸せになりますように」。お釈迦様に、インダス川に、チベットの山々に向かって、幾度も心の中で唱える…。 チベット仏教のマントラで、大乗仏教において、自分を取り巻く全ての生き物の幸せを願うことで、自分自身も幸せに導かれるというものです。心がけるのは「良いことを考え、良い行いをし、良いことを話す」こと。ラダックの人々は小さな頃から、家族と共に、自然や生き物たちと共に、暮らしを通して、こうした学びを身につけてきました。
高山病に苛まれ、頭が回らず、体が動かない中で、不思議と心だけが澄んでいました。出会った人々の言葉が、優しく心地よく心に染み渡ります。「一匹の虫を敬うこと、それ自体が私たちの一部でもあるのだ」、「楽しみを分け合えば、もっと楽みが増えていく」。人に優しく、怒らず、人を羨ましがらず、まずみんなの幸せを願う。そんな人たちの中に身を置くことで、自分自身の心が変化していく、そんな感覚に囚われました。
たった9日間でしたが、今回の旅は、人生の宝物です。心に受け止めた微風のような感覚を、棚に仕舞わず多くの人にお裾分けしようと思います。きっと、その喜びが何倍にも膨らむでしょうから。(じゅんこ)
●3日目の夜、スカルマさんの妹、ラモさん宅でディナーをいただいた時、ラモさんのお子さんが伝統楽器を弾いてくださったり、また一緒に訪れていたオシも彼の弦楽器をあるストーリーに沿って奏でてくれました。その時に全く想定もしていなかったことが、ワタシの中で起こったんです。
オシが2曲目に日本の『故郷』を弾いてくださって、そこに居たみんなで自然と歌い始める感じになったので、ワタシも歌おうとした瞬間に、涙がどうしても止まらなくなって、結局一節も歌えないまま、ただただ号泣していました。
日本を離れて、縁あってアメリカという土地に人生の半分以上住んでいますが、日本に帰るたびに体調は崩すし、重たいエネルギーと常に苦しさがあり、日本に対して正直あまり心地いいイメージを持っていませんでした。みんなの歌う故郷を聴いて、溢れてきた涙で気付いたのは、紛れもなく日本のことを心から愛しているんだな、ということでした。ただ、崩れいく日本や、苦しそうに生きている日本の方たちを観るのが辛くて、目を背けてきただけでした。
それが、ラダックから帰ってきて振り返ってみた時に、あの想いは日本に対してだけのものじゃないかもしれないと改めて気付いたんです。チキュウ自体がワタシ(みんな)のふるさとで、想う気持ちや愛も同等のものが存在しているんだと。そして、きっとこのチキュウへの愛っていうのが、今回ラダックで出逢った全ての人(ツアーでご一緒できたみんなも含め)に共通していて、それがみんなの内側から輝き出していたから、一緒に共鳴して魂を揺さぶられるようなことを、たくさん経験することができたのかもしれません。
「懐かしい未来」のラダック。IMAとMIRAIは重なっている。だからこそ、今どう生きるか。全生命体、生きとし生けるものと、チキュウとトモに、どう生きるか。それが鍵なんじゃないかなと想いました。(さおり)
●今回の旅の一番の目的は、ワタシの中の“懐かしい未来”とは?、それを探ることでした。現地で色々な人たちから、今の現状や彼らの想いなど、たくさんのお話しを聞かせてもらい、昔からの生き方を守ろうとする動きと、物質社会へ切り替わる動きの狭間での人々の葛藤を感じました。
その中でも、若い世代の子たちが、その混沌とした状況にあっても、彼らが一番大切にする愛や情熱からくる決断や行動を信じて進んでいる姿を見た時は、どこまでも広がる明るい未来への可能性を感じました。彼らの全身から溢れる熱い想いに、ワタシがメキシコや日本で会ってきた“キラキラ星人が、ここにもいる!“と感動でした!
さらには、日本から近いようで、それでも今まで触れたことのなかったチベット仏教の世界を感じることができ、それはとても興味深かったです。ときに滞在先の宿にある祈りのお部屋で祈りを捧げ、瞑想をし、心穏やかな時間を過ごさせていただきました。また、現地の人たちの優しさと心のこもったおもてなしに触れることができたこともとても感動しました。そしてなによりも、ヒマラヤの山々に囲まれた見渡す限りの壮大な自然の景観に圧倒されました! 今回のこれらすべての経験を通してワタシの目指す“懐かしい未来”のヒントが見えてきた気がします。そしてそのために、ワタシができること、今からどんどん始めていきます!!
ツアーでご一緒した素晴らしい仲間たち、皆さんの地球意識の高さと真摯に学ぶ姿は素晴らしく、常に刺激をいただけました。これまで出会う機会がなかった、色々なフィールドで活動する皆さんとの出会いは、ワタシのこれからの視野と活動範囲の広がりにつながっていくんだろうなと、その未知の可能性に今からワクワクしております。ジュレー!(あきてぃ)
●私の人生のテーマは、「どこで、誰と、どんな関係で暮らし、何でお金を稼ぎ、何を大切に生きていくか」である。とりわけ、「何でお金を稼ぐか」は生き方そのものに関わる重要な問いだ。
ラダックの人の平均月収は、農村部で1万円から4万円だそうだ。日本とは経済環境が大きく異なるが、貧しいと感じたことは一度もなかった。なかでも強く心に残ったのは、「祈ること」である。人々の生活には「祈り」が日常の中に自然に溶け込んでいた。私にとって「祈ること」は、大地とつながりを感じる行為である。ラダックの人々の暮らしは、まさに「祈り」に満ちていた。
そして「祈ること」から派生して気づいたのは、ラダックでは“自己と他者の境界”が日本とは異なるということだ。「パスプン」と呼ばれる、地域共同体のあり方は、その一つの現れであろう。人々の生活に触れ、暮らしを垣間見た旅の時間は、私にとって何よりの贈り物だった。日本で語られる「地域共生社会」や「共助」「相互扶助」といった言葉に対する違和感が、感覚的に溶けていくようだった。
また、今回の旅では、“プラネット・ローカル会議”への参加をはじめ、数多くのアクティビストへのインタビュー、そしてスカルマさん、辻先生、旅の仲間たちとの語らいを通して、これからの人生の旅路につながる多くの示唆を得ることができた。それらの体験は、これまで抱いてきた私自身のテーマをより鮮明に浮かび上がらせ、再び動き出すきっかけとなるに違いない。そう、今回の旅は、私にとってまさに「アンラーニング」だった。労働と消費の都市である東京で疲れた自分が再び息を吹き返し、大切にしてきたものの輪郭をもう一度確かめられた時間でもあった。(まさよ)





















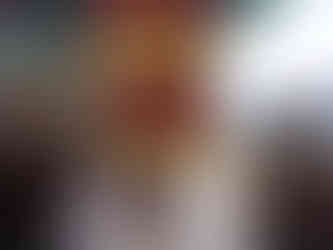






コメント