仏教哲学からひも解く「本当の幸せ」とはーゲシェ・コンチュク・ワンドゥ教授のインタビューから
- ナマケモノ事務局

- 2025年11月8日
- 読了時間: 10分
更新日:2025年12月12日
9月1日~9日まで、ナマケモノ倶楽部とジュレー・ラダック共催で、「"懐かしい未来"の故郷で、豊かな自然と文化の未来をみつける旅」を開催しました(ツアー詳細はこちら)。
数回に分けて、旅の日記と、貴重なインタビューなどをこの「ナマケモノしんぶん」でシェアしていきます。私たちが実際に目でみて、村に身を置き、人々の話から感じた学び・気づきをみなさんが受け取り、これからのローカリゼーション運動の知のツールとして活用いただければ幸いです。(事務局)
2025年9月7日夜、シェイ村「パラダイス・シェイ」にて
お話:ゲシェ・コンチュク・ワンドゥ教授
通訳:スカルマ・ギュルメット
文字おこし・編集:会津順子

誰しも、幸せを作るために行動するもの
グローバリゼーションとローカリゼーション、この2つはとても大きなトピックです。これらをしっかりと理解するために、「幸せとは何か」という視点からお話したいと思います。
ラダックは、仏教の教えや哲学のもとで、伝統文化が紡がれてきました。ラダックの人々の生き方や文化については、少なくとも1000年前から記録があります。実際は、それ以前から仏教を根っこに人々が暮らしていたことは間違いないのですが、記録がありません。
皆さんは、それぞれの場所からここに来ていますが、その理由は「なんらかの幸せを作るため」ではないでしょうか。私たちはどんな会社で仕事をしていても、たとえばGoogleのCEOやアメリカ大統領であっても、「苦しみを減らし、幸せを増やしたい」と思って行動しています。
ラダックにはこういう慣習があります。寝ているときに小さな虫が近づいて来たら、自分が幸せになる機会を与えられたと捉え、虫を殺さずに自分がそっと横へ移動します。そのような些細な行為で、私たちは日々、ちょっとした幸せを自分で作ることができるのです。
グローバル化が社会に苦しみを呼び込んでいる
20世紀から21世紀になり、ローカルを基盤とした伝統社会から、グローバル化された社会となりました。そのことによって様々な問題が起き、今、世界各地でローカルに回帰しようという運動が起きています。なぜ、もう一度、ローカルへと戻ろうとしているのか。それは、人々が幸せの本質を理解できていなかったことに気づいたからではないでしょうか。
幸せには二種類があります。一つは「身体的な幸せ」、もう一つは「精神的な幸せ」です。同様に、苦しみにも「身体が感じる苦しみ」と「心が感じる苦しみ」があります。ヨーロッパ諸国や日本、韓国などの国々は、目覚ましい発展を遂げました。しかし、心の幸せを無視して、物質的な幸せのみ追い求めてきた結果、現在、人々は様々な課題に直面しています。日本やヨーロッパが悪いと言っているのではありません。幸せとはどういうものかを考えてもらうために、事実をお話しています。
一方で、みなさんが今回の旅で体験した通り、私たちラダック人も、以前よりはいろいろ変化しています。それでも、お年寄りの世代は、今でも幸せの本質、幸せの哲学が身についています。彼らが暮らしの中で一番に据えているのは「心の幸せ」です。これは私が年配者の話を聞いて回ったなかで明らかになりました。
しかし、ラダックでも、若い世代は物質的な幸せに傾倒しています。グローバル化が進むヨーロッパや日本の影響を受けつつあります。私が皆さんにまず伝えたいことは、「物質的な幸せ」を目指して、いろいろな事業や開発を行ってきたことが、実は、自らの社会に苦しみを呼び込んでいるということです。
自己中心主義で発展する世界から、喜びを分かち合う世界へ
ラダックでは外国のような開発や発展がなくても、みなシンプルに生き、人々はとても幸せでした。しかし今ではラダックでもうつ病になったり、若い人が自殺したりということが起きています。これらは、グローバリゼーションという、外から来る新しいものでラダックを変えよう、良くしようとしたことが引き起こした結果です。
グローバリゼーションという言葉を口にしながら、ロシア、日本、インド…、どの国の指導者も「自国ファースト」で行動しています。そこには「慈悲」の気持ちはなく、みな自己中心的です。それぞれの国が、他の国よりも強くなりたいと、自国の利益にのみ集中し、他者を考えない、そんな構図に陥っています。
チベット仏教哲学では、自我が強すぎることが苦しみを生み出すと考えます。財産や家など自分の外側のいろいろなことに執着し、自分の心の幸せを大切にしないと、苦しみは続きます。たとえば、目の前に水しかなくても、家族みんなで飲むと幸せな気持ちでいられます。一方で、豪華な家に暮らし、贅沢な料理が並んでも、心が満たされていなければ、それらは全く役に立ちません。
物質的な幸せと心の幸せについて、ここに2冊の子ども向けの絵本があります。これらを読めば、幸せの扉を開くことができるでしょう。
ラダックの子どもたちの笑顔は幸せの象徴
辻 :このデズモンド・ツツ大主教とダライ・ラマ法王の対談を収めた「ミッション・ジョイ」という映画は、日本語字幕でも上映されています。素晴らしい映画です。「ミッション・ジョイ」とは、私たち人間が生きることに、もし使命(ミッション)があるとすれば、それは喜び(ジョイ)であるということです。最近、日本人でジョイフルな人を見かけません。でも、我々は、昔はもっとジョイフルだったはずです。
ゲシェ:私が小さい時に、ヨーロッパからの観光客がこう言いました。
「あなたの顔から幸せが見えます。ラダックの子どもたちの顔を見れば、あなた方がどれだけ幸せに生きているのかがわかります。私にはそれがわかるけど、あなたたちは自分でそのことをわかっていないでしょう?」
辻:それがまさにヘレナの言うポイントです。昨日、一昨日と、ぼくたちはシャラ村に行きました。村人たちが本当に幸せそうで、一体それはどうしてなのかと思うわけです。日本人はあんなふうになれない。でも、確かにちょっと昔を思い出すと、ぼくたち日本人ももっと幸せそうだったなと感じます。
ゲシェ:インド政府の偉い方々がラダックを訪れた際にも同じことを言っていました。ラダックの子どもたちは幸せに見えると。
スカルマ:そんなに幸せに見えますかね。私は自分ではよくわからないです。でも、子どもたちは目がキラキラしていますよね。それが幸せそうに見えるんですね。
ゲシェ:私も当時はわからなかったけれど、今、振り返ると、確かにそうだなと思うようになりました。


幸せの本質にある「縁起」
仏教哲学で大切な教えのひとつに、「縁起」があります。サンスクリット語で「プラティーティヤ・サムウトパーダ」と言い、すべてのものはつながっているという意味です。 縁起を大事にし、常に自戒することが、幸せになるか、不幸せになるかに関係してきます。
この縁起の考えでは、現代社会に暮らす私たちは、自分のおかげで自分が幸せになっている、自分のせいで自分が苦しんでいると信じ込んでいると指摘します。本当の幸せは、自分が何かをしたから幸せになるというものではありません。誰かが向こうにいて何かをする、そのことと私たちがつながっていて、それで自分が幸せになるのです。同じように、苦しみがやって来ても、自分のせいで苦しんでいるのではなくて、何かがどこかにあって、それと私たちがつながって、自分たちが苦しんでいるということなのです。
近年、ダライ・ラマ法王のおかげで、世界約65ヶ国の組織や大学の方々と仏教哲学者たちが、様々なテーマで議論を交わす場が持てています。本来は、私たちが先進国の方々から教わるべきなのですが、対面で話をしてみると、私たちの考え方を聞いた彼らが、涙を流すほど幸福について理解を深める結果になっています。
辻:先住民の言語には主語と述語はないんですよね。だからラダックでは、いわゆる西洋の科学が発展しなかったとぼくは思っているんです。一方、西洋は主語と述語がはっきり分かれている。主語は疑いようのない実体だというところから出発するから、西洋では科学がすごく栄えた。
でも、その西洋科学的な世界観が今、行き詰まっているんじゃないか。だから、実体を超えた仏教の考え方が大事になってきているということですね。

ラダックで学んだ「パスプン」「ジェスイラン」とは
参加者: このツアーに参加して、「パスプン」と「ジェス イラン」という言葉を知りました。特に「ジェスイラン」の「私」という概念がないところにすごく驚きました。また、シャラー村に滞在して感じたことは、人々の生活にお祈りが密着していることです。
私はソーシャルワーカーなので、人の生まれてくる場面と、死ぬ場面にたくさん立ち合います。そういう場面では、祈るしかないこともたくさんあるわけです。でも、今の日本の生活では、祈りの大切さを感じられない人がたくさんいます。日本ではご飯の前に「いただきます」と手を合わせる文化があり、海外の人にはとても驚かれます。日本にも祈りがあったわけです。どうしたら祈りを取り戻せますか。
ゲシェ:まず、2つの大事な考えについて理解ができたことはとてもよかったですね。「パスプン」については、『懐かしい未来』でもヘレナ・ノーバーグ=ホッジさんがしっかりと書かれています。私が話した仏教哲学でいう「縁起」そのものです。ラダックでも村によってパスプンの形が少しずつ違います。パスプンを説明をすると何時間もかかるので、ここでは割愛しますが、これが間違いなく社会科学であることを、今の若者たちに伝えています。
「ジェス イラン」とは、執着を手放すということです。現代では、自分が何かをすると「私がやりました」と自分を大きく主張します。けれども、私たちの伝統的な考えでは一歩下がる態度が美徳とされます。たとえば、私が大きな、良いことをしたとしても、「”私”ではありません」、「”私たち”がやりました」と言います。
スカルマ:確かに「私」ではなく「私たち」と言う文化はありますね。たとえば、誰かから「この家は誰のものですか?」と聞かれたら、「スカルマのものです」じゃなくて、「私たちの家ですよ」という言い方をします。
ゲシェ:また、誰かの小さな行動に対しても、「すごいことをやったね」と言います。これも「ジェス イラン」です。その行動じたいは小さくても、すごいですねと相手を尊重し、それを感謝の気持ちを込めてきちんと相手に伝えることで、自分が幸せになります。
「ジェス イラン」は、相手を批判するのではなく、素晴らしいねと言うことで、自分が幸せになるという哲学です。私はこの考え方が、現代のストレスやうつ病への薬になると、皆さんに伝えています。これは皆さんも勉強するべきだと思います。いろいろな哲学を比べながら、ぜひ勉強してください。
大事なのは、次の世代を担う子どもたちが、先進国の子どもたちと一緒に、一つの部屋で話し合う機会を作ること。そういう活動が互いを理解し、幸せの本質を学ぶ未来をつくるために大切だと考えています。
この活動をダラムサラ(インドのチベット亡命政府がある場所)で開催したときに、西洋の子がこう言いました。
「あなたたちは、お腹から笑っているように感じます」
「じゃあ、あなたはどこで笑っているの?」と私が聞いたら、「ここ(喉を指して)です」と。(笑)
■ゲシェ・コンチュク・ワンドゥ
1967 年生まれ。サブー村出身。南インドに再建されたチベット最大の僧院、デプン寺ロセリン大学にて仏教哲学を学び、チベット仏教学の最高学位である「ゲシェ・ラランパ」を取得。その後、ジャンムー・カシミール州のラダック語教本編集に携わり、2010 年からラダックの仏教大学CIBS(Central Institute of Buddhist Studies=仏教中央大学)にて教鞭をとる。2015 年に同11大学学⾧に就任。ラダックのオピニオンリーダーの一人。ヒンディー語、英語、チベット語、ラダック語などの言語に精通し、流暢に話す。


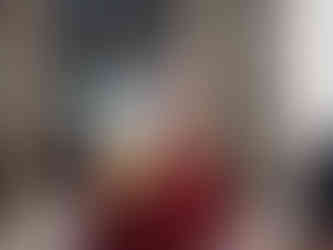






コメント