美しい文化の中で生きるとは?ーリジェネラティブ&ローカル・ツアー in 北部タイを終えて
- ナマケモノ事務局

- 2025年3月12日
- 読了時間: 16分
更新日:2025年4月8日
2月19日から4泊5日の「リジェネラティブ&ローカル・ツアー」から戻りました。17名の旅人と辻信一さん、ナマケモノ事務局・馬場の19名で訪れた北部タイ。森で育ったコーヒーの収穫お手伝いをし、伝統的循環農業「ク」について現場をみながら学びを深め、2つの村で合計3泊のファームステイもさせていただきました。お厘を鳴らし、自然と自分の内なる心と会話する静かな時間。各地で出会う人々の話を聞き、オレンジ色の布がまかれて得度を受けた木々の中にたたずみ、温かいごはんでおもてなしをしてくれるホストファミリーとの時間に、「自分にとっての美しさ、豊かさ、大切なものってなんだろう?」と問いかけるきっかけをたくさんいただきました。
参加したメンバーたちからの報告・感想、インタビュー文字おこしなどはまた改めてシェアしたいと思いますが、まずは事務局から全体的な旅のレポートをここに綴ります。(事務局・馬場)

【アティさんの藍染工房】
チェンマイ空港に集合した17人の旅人を迎えてくれたのは、カレン民族のオシさんと辻信一さん。2台のバスにわかれてまず向かったのは、チェンマイ大学図書館の中庭。プルメリアのかぐわしい匂いのなか、みなで円く座り、オシさんのリードで、自己紹介、この旅で何を得たいのか、好きなタイフードなどを言葉に出していきます。20代から70代まで、住まいも職業も、参加した動機もそれぞれ。でもみなこの旅で何かを学びたい、自分の暮らしに活かしたいという能動的なエネルギーを感じました。
そのあと向かったのは、ノンタオ村に行く途中、ツーリスト向けのエレファントキャンプやライン下りのスポットを抜けた小さな村です。車をとめてから、左にまだ冬休みちゅうの田んぼを眺めながら、土の道をのぼっていくと…、Attitaya Natural Indigoの看板と、二階建ての木造の小屋が。階段をのぼるなかで花壇や小さな畑が目につきます。迎えてくださったのは、自然染色家のアティさんとアティさんの友人で滞在中のフランス人、モニカさん。アティさんのもとで学んでいるブンさん。風通りが気持ちの良いテラスにはお米、野菜、フルーツたっぷりの手作りオーガニックランチが用意されていました。
午後にはセルフビルドで建てられたオーガニックな工房にて、エボニー(黒檀)とミョウバンをつかった草木染の体験もさせていただきました。道具も木製、手作りのものが多く、1Fのもみ殻を混ぜた土壁はひんやりして心が落ち着きます。
2Fに上がらせていただくと、そこには大きな窓と、足踏み式の大きな機織り機、そして完成した衣がハンガーラックにかかっていいます。1240本の経糸と4つのペダルで微妙な調整をしながら、織りあげていく作品はどれも一点もの。草木染につかう藍をはじめ、他の色の染料も畑で育てています。北タイにルーツをもつ父方、母方のそれぞれの伝統パターンを受け継ぎながら、ツーリストにもあうデザインも多数。生地のムダをださない縫製に心を配っていることが伝わります。「草木染にはきれいな水が必要。そして、その水をきれいにし続けるにはそこに住まう暮らしもオーガニックが求められる」という言葉に、私たちの存在が生態系と切り離せないことを思い出させてくれました。
「オーガニックで染めた色はヴィヴィッドさはないけれど、年齢を問わずまとえるのがよい」と話すアティさん。チェンマイの縫製工場で10年働いた経験もあるそうですが、そこでの機械的な労働には「何にもなかった」と振り返ります。一方、現在のアティさんはとても表情が生き生きとして、穏やかで、何より楽しそう。「毎日がホリデイのような気分。好きなことだけを好きなだけしていられるから」と話してくれました。

【レイジーマンコーヒーが育つアグロフォレストリーの森歩き】
「レイジーマンコーヒー」として、日本にもフェアトレードで輸入されている、アグロフォレストリーで栽培されたコーヒー生産の現場(森)を、生産者スウェさん、ノンタオ村の長老ジョクさん(68歳)と歩きました。コーヒーの収穫は12月からはじまっているので、2月末はすでに終盤。「ほとんど採り終わっているよ」と聞いていたものの、森の奥に入ると、斜面には緑の葉に隠れて赤く色づいた実があちこちに見られます。ジョクさんが背負ってきた籠に熟した実の見分け方、枝からのとりかたのコツも教えていただきながら、収穫お手伝いをしました。
実際、お手伝いして実感したのは、急斜面で身体を維持しながらコーヒー木の高い部分の実をとるのは大変だってこと。同時にコーヒー「だけ」の森ではなく、コーヒー「も」植わっている森の大切さ、コーヒーもフルーツだということ(熟した実をつまんで食べたらほのかに甘く、ジューシーだった)もわかりました。お昼はジョクさんの息子さんが建てたという、見晴らしのよい、森が一望できる小屋でのピクニックランチ。それぞれのホストファミリーが作ってくれたお弁当は、バナナの葉っぱで器用にごはんやおかずを包んでくれたものです。

昼食後のジョクさんのお話から:
・タイ政府はカレン民族への「先住権」を認めていない。
・政府が(勝手に)指定した森林保護区に現在4000世帯が暮らしている。なぜそうなったか。政府はが森を守る法律をつくったとき、そこで伝統的な営みを続けてきたカレン民族の存在を無視したからだ。
・ジョクさんはお父さんの代から30年、先住権・入会権や川の水脈・水源を守る活動をしてきた。
・この地区では伝統的循環農業「ク」は60年前になくなり、古いシステム(森の斜面を活かした森林農業)と新しいシステム(水田耕作)が共存している。カレン民族は斜面での農業を得意としてきたんだ。
・森の手入れはジョクさん、奥さん、ご近所さんと「助け合い」で行っている。
・この森ではハリナシミツバチが受粉に重要な役割を果たしてくれている。クモは害虫を食べてくれる。コーヒーの枝は少し剪定をする。5月の花が芽吹く1,2週間はとても美しい。
現在は3つの郡、4つの村(の森や庭)に生産者ネットワークが広がっているレイジーマンコーヒー。その取りまとめ役がスウェさんです。1つの村で1000kgから3000kgの乾燥豆の収量があり、小規模だけれど十分、とスウェさんは話します。「お金の神様、お米の神様、どちらも大事」と。換金作物ばかりに気をとられずに、自分たちの伝統である森のなかでお米をつくる(もともとは陸稲、水田耕作は近代になってから)生活様式も大事にしたいというメッセージは、日本でのお金を中心に動く消費社会での暮らしについて、私たちは何を忘れてしまったのかという宿題にもなります。
森歩きのあとは、乾燥所、Lazymanの刻印がある3キロ焙煎釜の見学やナチュラルプロセス、ウェットプロセスそれぞれの特徴などもお伺いし、さらに日本でコーヒー屋を営む2人がスウェさん焙煎のコーヒーをドリップして飲み比べをしたり。かと思えば、レイジーマンのスピリットにならい、ごろんと横になってお昼寝するメンバーも。ゆったりとした時間を過ごしました。このレイジーマンテラス2Fで民泊させていただいたメンバーもいたというから、うらやましいことです。

夜はホストファミリーたちがつくってくれた一品でキャンプファイヤー。村の子どもたちが「Lovely Garbage Band」として廃材を楽器にアップサイクルさせ、私たちのためにクルー先生とともに演奏をしてくれました。帰りは星空を眺めながらゆっくり歩いて帰りました。いい時間でした。
【長老ジョニさんとの時間】
DVDブック「レイジーマン物語」の表紙には、カレン族の長老・ジョニ・オドチャオさんが、森のなかで笑みを浮かべている写真が使われています。実際にお会いするジョニさんも、ジャケット写真と変わらず、自然体そのもの。六男でレイジーマンコーヒーを立ち上げたスウェさんの話には参加者と一緒に耳を傾け、ジョニさんも一言と、挨拶を振られると、辻さんと屋久島で出会ったご縁の最初をシェアしてくださる。ほとんどが初対面の私たちに「飲め、飲め」とローカル焼酎をすすめてくれ、日本語、タイ語、カレン語、英語が入り混じって、心は通じている気分になります。
2日目の午後には、辻さんのリクエストでジョニさんが管理しているレイジーマン・ガーデンを案内していただきました。移動は2台のピックアップトラックの荷台に分乗。だいぶこのスタイルに慣れてきた私たち。埃が舞うタイミングでは歓声があがります。


レイジーマンガーデンの入口に看板はなく、木の柵だけ。自然農な庭(というか林)を歩きながら、食べられる樹、植物を40種類ほど植えています。私たちが訪れたときにあったのは、カボチャ、ビーツ、ハト麦、ごま、唐辛子、タロイモ、他野菜・・・。「ほれ」とジョニさんから回され、食べられる葉っぱ、木の実などみなで味見をしながらすすんでいきます。竹などを燃やして灰になったところに唐辛子を植えるといいんだよとも教えていただきました。
レクチャーを受けれるような小屋もあり、カレン民族に伝わる宇宙観、人間の身体に宿る5つのスピリットと、自然界に宿る32のスピリットの話を伺いました。
カレン民族の伝統儀式の一つ、新生児のへその緒を木にしばり、その子はその木と特別な関係になるというお話。スウェさんの3人のお子さんはぜんぶこの木だよという場所にも案内していただきました。
ノン=池、タオ=倒れるという意味のノンタオ村。神様が魔物とけんかして押し倒された跡の谷間が村の由来なんだよと聞くと、本当に神様がばったーんと倒れたような光景が浮かんできます。足の先から頭まで1キロ、棚田になっている場所が片腕で、帰りには案内のオシさんがあれが頭だよとわざわざ車をとめて皆にその地形を見せてくれました。
ノンタオ村出発の朝には、各ホストファミリーにお別れをして、ジョニさんの家に集合。そこではサプライズの招魂の儀式が準備されていました。カレン語で「キチュ・コクラ(縄で魂を呼ぶ)」。(と聞こえましたが違ってたらごめんなさい)通常はカレンのお正月にあたる2月と8月後半に行われる儀式だそうです。お酒とお米とお供えものの花があり、ジョニさんが儀式の言葉を唱えたあと、1人ひとり、健康と旅の安全を祈って、魂がどこかにさまよってしまわないよう、白い縄を腕に結んでいただきました。
【ドイチャン・パペ村、伝統的循環農業「ク」の森を歩く】
ランプーン県バン・ホーン郡ドイチャン・パペ村。カレン民族の人々が聖なる山として大事にしてきた「象の山(タルー・クチョ)」が村の名前になっています。人口278人、78世帯。6つの集落で構成されるドイチャン・パペ村は、ノンタオ村から運転を引き受けてくれたバピさん、オシさんからみても「懐かしさを感じる風景」の村です。面積は21,000ライ(3,360ヘクタール)、ノンタオ村の約2.4倍の大きさで、そのほとんどが森です。
この村を訪ねた理由は、ノンタオ村ではすでに途絶えてしまった、カレン民族の伝統的循環農業「ク」を学ぶため。それまで焼き畑、野焼きは悪い慣習だとレッテルを貼られてきたものが、今、実は世界中で「リジェネラティブ農」として再評価されつつあるのです。(タイではまだその評価がなく、誤解と偏見を解消しようと先住民族ががんばっている)
村の若きリーダー、ディープヌ―さんは、この森を文化保存地区(cultural preserved area)にしたいと語ります。それはカレンに伝わる伝統的循環農業「ク」を守り、自分たちにとって生活のすべてである水、森、土、そしてたねを守り、この村でこれからも自給的な生活を営んでいきたいから。実際、ドイチャン・パペ村では、7割がこの「ク」(ローテーション・ファーミング)で陸稲、コーヒー栽培、養蜂を軸に生計をたて、残りの3割を水田(近代農業)にしています。現金が必要なのはガソリン、塩、料理油、ガス代くらい。ほぼ自然に依存した暮らしが成り立っています。

1日目夜のディプヌ―さんのレクチャーから:
・「ク」として運用するのは森の11%だけ。
・そのほとんどは、火を入れたあと最低7年から10年は放置する(自然に森が再生していくのを待つ)
・「膝より下では伐らない」ことで土中の根を生かし、あたらしい生命(脇芽)が再生する仕組みを維持している
・ここ2,3年では、森の0.5%しか使っていない。
・チェンマイ大学との共同研究では、1つのクの畑ではかつて200種の食べられる森となっていた。現在は50種類くらい。
・ディプヌ―さんが大切にしている長老からの教え
「いのちを大切に」
「所有しようとするな」
「儀礼を大切に」
「米が大事だ」
辻さんからのコメント
「日本では9割以上、失われた智恵がここにある」

村でのホームステイの翌朝、実際に森を歩き、タイのテレビ局の取材チームとも途中一緒になりながら、火を入れたあと、気候のせいもあるのでしょう、もりもりと再生しつつある森の様子を「2年目の森「3年目の森」「数か月前に火をいれたばかりの畑」など見せていただきました。
ディープヌ―さんの説明から:
・「ここに火入れをしてもいいか?」と1本、枝を切り、山の神様に捧げものをして聞く。その晩の夢見がよければそこで続けてOK。悪い夢の場合はその場所では火入れをしない。
・木を伐るとき、草刈り、収穫などは村の共同作業として行っている。
「ク」のカレンダー
・2月:火入れをするエリアの木を膝丈で伐る
・3月:大きな木を切り始める
・4月:火入れ。一回の火入れは1時間以内。1週間の間にぜんぶ終える
・5月:種をまく月。陸稲の場合は2回だけ草刈りに行く。あとはほったらかし
・9月:ナス、キュウリ、唐辛子などの収穫
・11月:稲刈り。その後、1月くらいまでかぼちゃやタロイモの収穫
歩くなかで森での遊びや伝承(水が飲める木、ストローにもつかえる枝、食べられる実、ヘビは村の監視役)もみせていただき、森と生きるってこういうこと(観光のためのパフォーマンスではなく、暮らしの中のふつうの行動だった)なんだなと、感じました。
一方で、2月のこの地域はとても乾燥していて、自然火災やまた市街地に近いタイ人の農家の(伝統とは異なる)野焼きから山に火が燃え移る火災発生が多いことが問題になっています。ディープヌ―さんたちは村人有志で消防団を結成、防火帯をつくり、貯水池をつくり、定期的にパトロール&監視カメラで煙を探知して、山の上にある自分たちの村、そして森を守ろうとしています。
「政府が動いてくれないから自分たちで動く」、その決意と情熱に、村を発つ前の短いプレゼンテーションでしたが、心を動かされました。
【コーヒーを通じてローカル経済を世界に発信する、先住民族の若い世代に希望をみる】
最終日は「チェンマイ市内のカフェめぐり」。旅の前半でみてきた山岳先住民族が森の中で育ててきたコーヒーが、どう国際都市チェンマイのカフェで提供されているのかを学ぶプログラムです。コーヒー通でもある辻信一さんの「ここは外せない」と推薦いただいたのが、アカアマコーヒーとTOKIコーヒーの2つ。オシさんの細やかなアレンジのおかげで、午前はチェンマイ郊外にあるアカアマ・リビングファクトリー Akha Ama Living Factory に向かいます。
緑の木々に囲まれたファクトリーのテラス席に座り、若いスタッフたちが淹れてくれたコーヒーで「今、ここ」にチューニングした後、2Fのミーティングルームで、アカアマコーヒー代表のアユさんに直接お話を聞くことができました。伝統文化を大切にしてきた上の世代と若い世代を「森林栽培コーヒーの起業」でつなぎ、教育とエコロジーで役割を果たしていきたいというアユさんの強い思いが伝わるお話でした。

従業員の4割が先住民出身の若者であること、コーヒーだけでなく養蜂や柿、梅、お茶など、伝統農業の作付けカレンダーの再教育にもなっていること。生姜の単一栽培をしていた叔父さんの畑の一角で、3、4年か.けてコーヒーと森の多様性を取り戻し、そのビジョンを他の農民たちが自分の目で見ることで、アカアマ・プロジェクトが何を目指しているのかを理解してもらえたこと。そうやって少しずつ広げてきたここまでのストーリーを、等身大の言葉でシェアしてくれました。
「農民の生産物(コーヒー)を売らせてもらっている」「アカアマプロジェクトのステークホルダーには農民がいる」「都市と農村をつなぐチェンジ・エージェントでありたい」「伝統的な価値観にある美しさを大事にしたい」という表現に、アクティビストとしてのアユさんの思想の奥深さを感じ、質疑応答の時間も活発でした。
訪問したのは、Akha Ama Living Factory
チェンマイ市内にあるカフェ Akha Ama Coffee
東京にも店舗がある Akha Ama Coffee Kagurazaka


午後はチェンマイ市内のTokiコーヒーへ。心づくしのカレン民族と北タイのランチをいただいた後、カレン民族の若き店主トキさん(30歳)と奥さんのナーンさんが淹れてくれたコーヒーを飲みながらお話を伺いました。
トキさんはノンタオ村より北西に車で3時間先にあるガラヤニワッタナー郡の出身。コーヒーの師匠は村の長老・トンディさんです。トンディさんはコーヒー農民、行商人、アクティビストという肩書をもち(ナマケモノ倶楽部の運動+文化+スロービジネスと通じるものがある!)、パガニョー(カレン民族)で最初に音楽をツールにカレンの文化・哲学を世界に発信した人とのこと。
この地域は、麻薬撲滅を掲げたタイ政府のロイヤルプロジェクトにより、1968年よりコーヒー栽培がすすめられてきました。トキさんはコーヒー農家としては4代目にあたります。ロイヤルプロジェクトではプランテーションでのコーヒー栽培が推奨されましたが、村人たちはそれにNOと言い、自分たちの伝統的な農法でコーヒーを植え始めました。とはいっても、カレンの人々にはコーヒーを飲む文化がありません。トキさん祖父の代には植えるだけ、父の代になってようやく実を収穫し、換金することが始まりました。
そしてトキさんたち若い世代が「自分たちのもつ文化にある詩的なもの、民話を大切にしたコーヒーを作ろう!」とアグロフォレストリーのコーヒーを自家焙煎し、市内のカフェで提供するというtree to cupのコーヒージャーニーが始まったところです。Toki coffeeのビジョンは、同時にコミュニティの人々に対してもインスタントコーヒーや化学肥料を使うことへの問い直し・再教育にもつながっていると伺いました。
ちなみに Toki coffeeという屋号を勧めてくれたのは、午前に訪れたアカアマコーヒーのアユさんだそう。先住民族のルーツをもつ若い世代が横につながり、都市部で活躍している姿に出会えたこと。ツアーを締めくくるのに最高の訪問場所でした。
終わりに
ナマケモノ倶楽部ででかける旅は、自分自身が変わる旅。日本に帰ってから、旅先で受け取ったメッセージを、参加メンバー1人ひとりがどう消化し、世界の見方、自分の暮らし方に反映させていくかが、本当の旅のはじまりです。それぞれのペースで旅で感じたこと、日本に戻って考えはじめたことを周りにシェアしたり、新しく何かを始めてみたり、リジェネラティブ&ローカルな一歩を踏み出してもらえたらなと思います。
その道筋を誘ってくれたノンタオ村、ドイチャン・パペ村、チェンマイで迎えてくださった皆さん、このプログラムがfruitfulなものになるよう、心を砕いて準備してくれたカレン民族の友人オシさんと、「まなそび(学び遊び)」の極意を示し続け、インタビューや説明のすべてを日本語に通訳・解説してくれたナマケモノ教授こと辻信一さんに感謝の気持ちを記したいと思います。ありがとうございます。







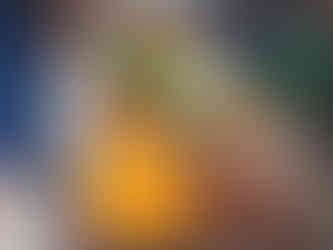














































コメント