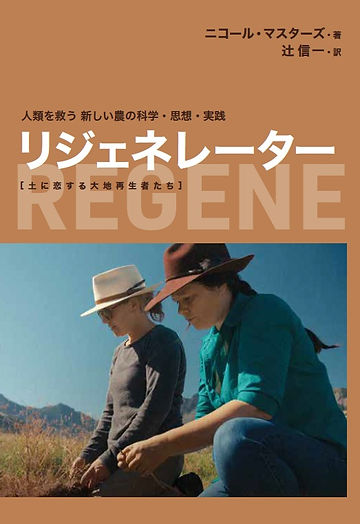今月のスローな人・モノ・コト
南米エクアドルで、森をよみがえらせ、土と生きもの、人々の平和を紡ぐ「大地再生チョコレート」。
ナマケモノは生態系の中にとけこんで、森に育てられ、森を育てる。このナマケモノの生き方にこそ「リジェネラティブ=おのずから更新し、再生し、いのちをつないでいく生命の営み」がみごとに表現されています。
現在、世界中で、土を掘り起こさない、常に土を覆う、動植物・微生物の多様性を保つ…などを柱とするリジェネラティブ(大地再生)農業が注目されています。待ったなしの気候危機を前にして、農民だけでなく、山や海に、そして都市に暮らすすべての人に、リジェネラティブな世界観と生き方が求められています。
ナマケモノ倶楽部は、「大地再生チョコレート&コーヒー」をキーワードに、国内外の土と森をよみがえらせ、ローカルな食と農、コミュニティ活動を応援します。
>>特設ページはこちら。
>>ウェブショップご注文はこちら。

3月4日(水)夜、オンライントーク開催!
「Local is Beautiful インド北部・ラダック 旅のフィールドノート報告会」
スカルマさんからは、ラダックに迫りくるグローバル化の波について、一方、NPOジュレー・ラダックが取り組む農村プロジェクトを通じたお母さんたちや農村での暮らしを、辻さんからは、20年前から通い続ける農村部の変わったこと・変わらないことや、国内外のローカリゼーション運動の現場を訪ねている視点から、なぜ今ラダックが重要なのかについてお話いただきます。
ラダックに行かれたことがある方はもちろん、ローカリゼーション運動に関心があるみなさんもぜひご参加ください。「懐かしい未来」への道筋を一緒に取り戻し、クリエイトしていきましょう!
>>イベント詳細はこちら
\募集開始!/“懐かしい未来”エコカルチャー・ツアー in ラダック
~早春の羊飼い体験&伝統文化とコミュニティの智恵に学ぶ旅
5月5日~12日、インド・レー空港集合解散
40カ国語以上で翻訳された世界的ベストセラー『懐かしい未来』の舞台、ヒマラヤの“小チベット”、ラダック地方で、伝統的な羊飼いの暮らし体験を通じて、文明の岐路に立つ私たちにとって本当に大切なことは何かを再発見する旅に出かけませんか?
ローカル経済、文化再生に焦点をあてながら、農村部へのホームステイ、ラダック識者やローカル活動家たちへのインタビュー、伝統医療やチベット仏教の寺院訪問を通じて、ラダックの人々が世界を覆い尽くすグローバリゼーションの波のなかで、本当に大切なことをどう見極め、次の世代に手渡そうとしているのかを五感を使って学んでいきます。
早春のラダックは、雪が解けた大地にいのちが芽吹き、羊が嬉しさでジャンプしながら草を食む素敵な季節。先住民の伝統的な智慧、遊牧民や農耕文化、お母さんの活躍、ローカル経済の再生といったキーワードやテーマに関心のある方、この特別な機会にぜひご一緒しましょう!早割、ユース割あり。ぜひお気軽にご相談ください。
>>ツアープログラム詳細はこちら。
新刊案内
『リジェネレーター 土に恋する大地再生者たち~人類を救う 新しい農の科学・思想・実践』
農業生態学(アグロエコロジー)の教育者、コーチ、システム思考の思想家として、オーストラリアや北米で「土壌健全化プログラム」の指導を行うニコール・マスターズによる『For the Love of Soil』の日本語版が、ゆっくり堂から刊行されました。
この危機の時代に、土壌と人間の健康を育む農と食を蘇らせるべく、喜々として励み、高い生産性と収益性をもつ農地をつくり出してきたリジェネレーター(大地再生者)たちの物語。
>>ウェブショップご注文はこちら。
>>特設ページはこちら
「ニコールのように、土壌の健康、植物の健康、動物の健康、そして人間の健康のつながりをすべて見事に結びつけてみせた人はいない!」
ゲイブ・ブラウン
<催行決定>2026年2月18日(水)~23日(祝)
リジェネラティブ&ローカル・ツアー in 北部タイ
森の民が紡ぐ伝統農業とローカル経済を体験する旅
森とつながり直すことから、足元の土を見つめ直すことから、世界を変えていきませんか? ナマケモノ倶楽部と出かける「リジェネラティブ&ローカル・ツアー」は、世界各地で、コミュニティと生態系の再生に取り組む人びとに出会い、その暮らしや文化を体験することで、自分のなかに眠っていた可能性を再発見し、世界を見る新しい視点を見出し、これからの生き方に活かしていこうという創造的なプログラムです。
>>詳しいツアープログラムはこちら。
リジェネラティブ&ローカル・ツアーin ラダック、学びの旅の報告
9月1日~9日まで12名のメンバーと辻信一さん、ナマケモノ事務局で訪れたインド、ラダック地方。その学びのシェアが連載形式でまとまりました。
参加者個々人の目線から毎日のできごとを書き記したフィールドノートです。ジュレー・ラダック代表スカルマ・ギュルメットさんのアレンジで実現したキーパーソンへのインタビューも掲載。ぜひローカリゼーション運動のツールとして活用していきましょう。
>>連載一覧へ
大学での教員生活を終え、時間に余裕ができた辻さん。ナマケモノ倶楽部ウェブサイトにブログを綴っていただけることになりました!スローな思想、世界で起きている問題や話題から考えていることなど、気軽に綴ります。
>>辻信一のブログを読む

スロー思想の奥深い「ムダ」の世界を、ナマケモノ教授と一緒にてつがくしてみませんか?
コロナ禍では「不要不急」がひとつのキーワードとなった。また「コスパ」「タイパ」、そんな考え方が日常を侵食している。しかし、要不要とはいったい何だろう。身のまわりのすべてのことを、「役に立つかどうか」「効率がいいかどうか」「払った対価に見合っているかどうか」、そんなモノサシで測ってよいものだろうか。
その価値観で捨てた「ムダ」なもの、それは本当に「ムダ」なのか?誰にとって?何にとって?そもそも「ムダ」で何が悪いのか?「ハチドリのひとしずく」を日本に紹介した著者が「ムダ」を切り口に、暮らし、労働、経済、テクノロジー、人間関係などについて思索する。
>>ご注文はこちら
>>特設ページつくりました。一緒にムダ活しよう!
土が蘇る、人類の希望が蘇る
話題のリジェネラティブ・ムービー
ついに日本上陸
「リジェネラティブ(大地再生)」という世界観と出会い、農業・漁業・牧畜を、そして生き方そのものを転換した人びとに迫るドキュメンタリー映画、『君の根は。大地再生にいどむ人びと』の日本語版が2022年秋に完成、各地での上映会が始まりました。2025年1月現在、400か所で上映会が企画され、延べ10400人の方が参加しています。
誰でも自主上映会を企画して、この希望のメッセージを広めることができます。この映画をツールに大地再生ムーブメントに参画しませんか?
>>映画特設ページはこちら
>>予告編を観る
これは単に農民の運動ではない。地方に住む人も、都会に住む人も、山に住む人も海辺に住む人も、誰もがみな、人間観、自然観、世界観の転換を迫られている。あなた自身が当事者なのだ。辻信一
>>全文を読む「答えはすぐ足元に 映画『君の根は。』に寄せて
辻信一さん新刊『サティシュ先生の夢みる大学』
現代を代表する思想家、教育者、 エコロジスト、平和運動家、 サティシュ・クマール。そのサティシュが設立した、 現代エコロジーとホリスティック思想のハブとして名高い英国シュ ーマッハー・カレッジ。辻信一とそのゼミ生たちが、 サティシュをはじめとする賢人たちと過ごしたシューマッハーで夢のような”学びの一週間”を丹念に記録したドキュメンタリーが『サティシュ先生の夢みる大学』として、ゆっくり堂から5月30日に刊行されました。本を通じて旅を追体験し、「本当の学び」について思いをめぐらせてみませんか?
----------------
「あのとき感じたワクワクは今もずっと続いている。サティシュ先生と過ごしたシューマッハーカレッジでの一週間が、私たち学生の人生を変えた!」
(本書にも登場する元ゼミ生、kaeさん)
-------------------
>>書籍のご注文はナマケモノウェブショップから
>>ゆっくり堂の特設ページはこちら

『自然農という生きかた』(川口由一+辻 信一)
耕さない、草や虫を敵としない、肥料を持ちこまない、を基本とした「自然農」を確立し、学びを求めてくる人に分け隔てなく「自然農という生きかた」を伝え続けてきた川口由一さん(2023年6月逝去)に、ナマケモノ教授こと辻信一さんが、自然農とは何か?、自然農という答えにたどりつくまで、漢方と自立への道について、じっくりお話を伺った対談集。2011年に大月書店より刊行された『自然農という生き方』に、2022年11月、奈良のご自宅を訪ねてのインタビューを収めた、待望の増補改訂版です。
リジェネラティブ(大地再生)農業が世界で注目されるなか、土と向き合い、「いのちの道、人の道、我が道」を追求されてきた川口さんから紡がれる言葉に耳を傾け、自然の理に沿った自然農という生きかたへの道しるべにしてみませんか?
>>特設ページはこちら
>>ご注文はこちら
>>グループや小さなお店向け「小さな卸」ご注文はこちら
ナマケモノしんぶん 新着記事
書籍案内
『大岩剛一選集 ロスト&ファウンド懐かしい未来の風景と建築』刊行!
建築家、環境運動家として数々の仕事を残してきた大岩剛一氏(2019年4月逝去)の生前の文章が、貴重な写真やイラストとともに、ナマケモノ関連企業のひとつ、ゆっくり堂より出版されます。
高度成長期の都市部で私達が手放してしまった風景と2000年以降のエコロジーへの関心の高まりのなかで、日本の伝統建築技術とあわせたストローベイル工法など、剛一氏が情熱を注いだ「懐かしい未来」への思想と実践が綴られた一冊となりました。後半ではコミュニティデザイナー・山崎亮氏と編者で剛一氏の弟、辻信一との対談も収録されています。
これからの建築とコミュニティ、暮らしのあり方を考えたいすべての人におすすめします!
「レイジーマン物語ータイの森で出会った"なまけ者"」
(DVD71分+ブック72ページ、ゆっくり堂)
カレン族の民話のヒーロー、「レイジーマン」が現代に蘇った。中南米の動物ナマケモノに出会ってから25年、ぼくはタイ北部の森で、今度は、自らを“なまけ者”と呼ぶ人間たちと不思議な縁で結ばれ、スローライフの極意を伝授された。ーー辻 信一
少数民族を襲った戦争、麻薬、貧困、自然破壊…。絶望の淵から立ち上がり、カリスマ的な指導者となったジョニとその一家の物語を、足かけ5年をかけて撮影。美しい音楽・映像で綴られるインタビューをぜひご覧ください。ブックは書き下ろしの文章、解説で読み応えあり。

“友産友消”とは、友だちが生産したものを、友だちで消費すること。どのくらい仲良しだと“トモダチ”なのか? 友だちどうしの「生産」と「消費」の先に、どんな未来が待っているのか?
まだ定義ははっきりしないけれど、友産友消=トモトモが「なんだか楽しそう!」とひらめいちゃった人たち、すでに実践している人たちの「物語(ストーリー)」から新たなトモトモの関係性が生まれたらいいな。
>>特設ページへ